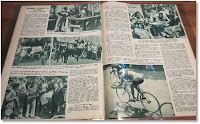.
.
Le Miroir des Sports誌
1935年7月25日号
ツール・ド・フランス第16ステージ
ーーー ◇ ーーー ◇ ーーー ◇ ーーー
12~13ページです。
(茶色の文字が写真の説明文です。)
12ページ上の写真
ピレネーの峠、そしてポーへ、ずっと励まし合ったコンビ
ティアーニはロシアンビリヤードに興じ、
さらに日焼けしたモレリは自分の番を待っている。
(※) キューを立て気味に持っているのがモレリ
|
12ページ中段の写真
左写真:
アンリ王時代の古都(※1)の当時の二頭立て荷車
アールツは、二頭の牛と遅さ比べを始めた。
右写真:
荷台に乗っかっているのは、左から右へ、
ベルトッコ(※2)、ガルシア(※3)、ベノワ・フォーレ(立っている人)、
ポール・ショック、ジャン・アールツ
|
(※1) ポーは、アンリ4世の生まれ故郷のようです。
アンリ4世は、日本でいうと安土桃山時代から江戸時代初期の人物で、
在位中から現代に至るまでフランス国民の間で人気の高い王の一人
だそうです。 https://ja.wikipedia.org/wiki/アンリ4世_(フランス王)
(※2) Aldo Bertocco アルド・ベルトッコ
フランス ツーリスト・ルーティエクラス参加
(※3) Manuel Garcia マヌエル・ガルシア
フランス ツーリスト・ルーティエクラス参加
12ページ下の写真
ピレネーでの自分の記憶を思い起こしながら、興味津々に記事読む。
左から右へ、3人のツーリスト・ルーティエ選手、
ベノワ・フォーレ、モクレール(※4)、ショック。
モン=ルイ、ピュイモラン、ポリテ・ダスペ峠、アル峠のステージ(※5)の
写真を見ながら思い出している。
|
(※4) Joseph Mauclair ジョゼフ・モクレール
フランス ツーリスト・ルーティエ参加
L’Union Vélocipédique de Reims ランス・ヴェロシペド連合のメンバー
だそうです。
(※5) 一つ前のステージ、第15ステージです。
13ページ上の写真
ポーの青空のもと、テラスでのひとコマ。
左から右へ、
ベルギー人ディグネフ(※6)と、3人のツーリストルーティエ達、
ファヨル(ニース)、リュオズィ(ニース)、ユベツ(ラン)(※7)。
彼らはデッドラインタイムをオーバーしてポーに到着したが、
コミッショナーによって救済されることになった。
|
(※6) Antoine Dignef アントワーヌ・ディグネフ ベルギー人、個人参加。
この年から開催されたプエルタ・ア・エスパーニャの第1ステージで勝利。
したがって、大会史上初めてマイヨ・ロホの袖に手を通した男。
だそうです。 https://ja.wikipedia.org/wiki/マイヨ・ロホ
(※7) Georges Hubatz ジョルジュ・ユベツ
フランス人、ツーリスト・ルーティエ参加
13ページ下写真
シャルル・ペリシェ
ピレネーで隠遁生活を決め込んでいた彼は、レース勘を呼び戻すことができるだろうか?
人気者シャルロ(※8)は、
1929年のツールで最終成績26位、1930年は8つもステージ勝利を挙げたにも関わらず、
優勝のルデュック(※9)、マーニュ、グエッラ(※10)らに及ばず9位、1931年は13位。
久々の出場となった今年は、初心に戻って出直しの年のようだ。
|
チャールズ・チャップリンのフランスでの愛称ですが、
ファーストネームのスペルが同じなので、
シャルル・ペリシェにも使われたようです。
(※9) André Leducq アンドレ・ルデュック
フランスナショナルチーム参加
(※10) Learco Guerra レアルコ・グエッラ イタリア人。
人間機関車と言われた名選手だそうです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/レアルコ・グエッラ
ーつづくー
この記事は、2016/8/18(木) 午後6:37にYahooブログに掲載した記事に
加筆・修正し再掲載したものです。