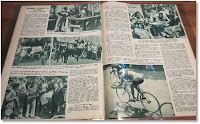.


Le Miroir des Sports誌
1935年7月25日号
ツール・ド・フランス第16ステージ
ーーー ◇ ーーー ◇ ーーー ◇ ーーー
14~15ページです。
14ページは水泳の記事です。15ページを解読しましょう。

15ページ上写真
(茶色の文字が解読結果です。)
あん? もっとカメラから離れろってか?
ムッシュー・アンリ・デグランジュは、
カメラマンにわざと噛みつくように言った。
”ツールの父”のその言葉に、
国内外のジャーナリスト、大会役員、アントナン・マーニュ(杖の人)の皆が笑った。
(※) アンリ・デグランジュは、こっち向いて噛みついている爺さんです。
15ページ中段は、記録一覧

15ページ下の挿絵
山岳地の寒暖の差の恐ろしいこと。
このステージのスタートでは半袖だったが、すぐに防寒服を着こむことになった。
選手が到着するまでの間、地元の写真屋のひな壇は団体客が絶えることがない。
街道の巨人が宿泊するホテルの前では、
若いファンが直筆サインをもらおうと待ち構えている。
RED TdF 1935
(※) REDというのは、当時の画家、漫画家です。
「ツールドフランスの画家、漫画家」という本があって、
その中で紹介されています。
ミロワール・デ・スポール 長期間掲載
RED
ミロワール・デ・スポール誌のツール発展期の代名詞
古き良き時代のユーモアコラムのような素朴な視点
子供のころ親しんだポエムを思いだす筆致
ツールがくる日の皆のざわめき
ツールのきらきらした光景
大レースへの素直な賛美と、少し冷めた嘲い
本名ルネ・エミール・デュロン・ロワ(1894-1970)。
DERと署名することもある彼は、
15年もの間ツールの全コースをジャック・ゴデと一緒に回り、
REDの名でポエムの世界を展開した。
短時間で書き上げるため、硬い印象を与える細線の描写だが、
境界線をなくして、様々な場面を所狭しと書き並べるスタイルは、
どこから読んだらよいのかぼんやりしているが、
そこがまたこの絵の世界に合っていもいる。
ツールの画家、漫画家で有名どころのそろい踏みの図です。
REDは下段の右から3番目。
自転車にとどまらず多くの挿絵を描き、文字と写真がほとんどのスポーツ誌面に
遊び心を添えました。
ーつづくー
この記事は、2016/12/18(日) 午後5:02にYahooブログに掲載した記事に
加筆・修正し再掲載したものです。








 .
.